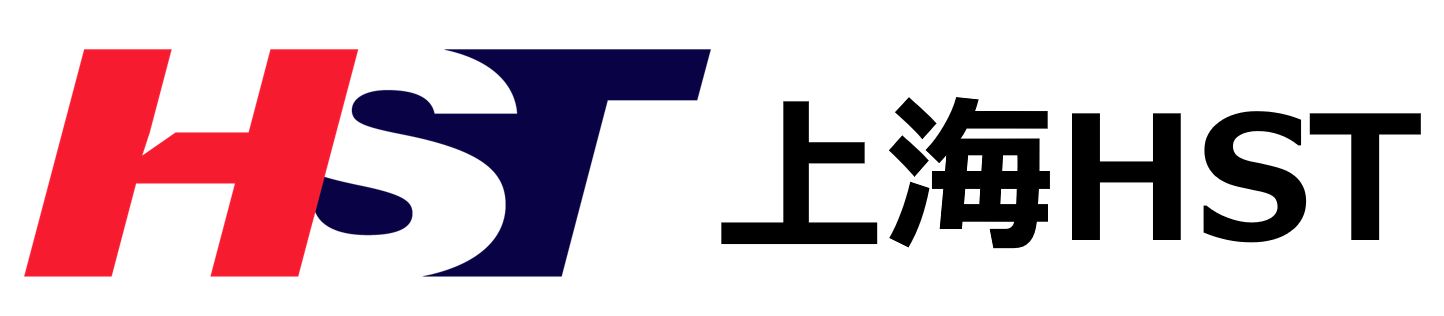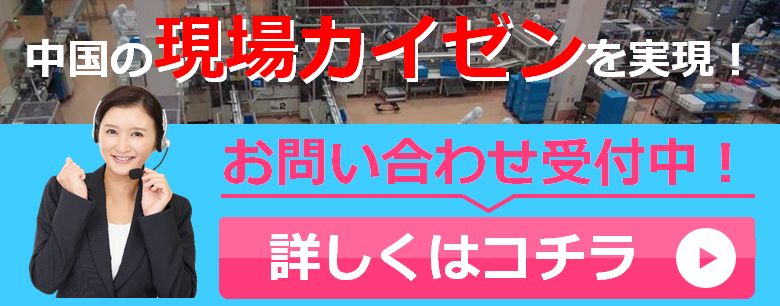弊社お客様の中には一般的な製品ラベル以外にGHSラベルなど特殊な製品ラベル発行を運用している場合もあります。
今回は過去のGHSラベルの導入事例を参考に手入力中心のGHSラベル運用からシステム運用でカイゼンしたポイントや発行作業に必要なプリンターの特徴と注意点を比較して紹介します。
システム化で間違い防止。GHSラベル発行画面イメージ

GHSラベルのフォーマットは導入する企業によって、必要な項目や効率化の観点からQRコードを追加し運用されています。
GHSラベル発行をシステム運用の変更で、表示項目を出来る限り自動表示化し手入力運用を省略する仕組みが実現できます。
製品コードの関連項目を自動表示化
製品コードを選択すると自動的に「製品名称」や「関連絵文字(シンボル) 」、「危険有害性情報」、「注意書き」が表示。
紐付けし関連した項目を自動表示することで、スタッフの手作業による選択ミスを防止し作業効率を向上させます。
関連日付はシステムで自動計算化
生産日付を選択すると製品別に異なる消費期限日を計算して自動的に表示。
製品ロット構成内に日付情報が必要な場合は、選択した日付を加味してロット構成を作成します。
ロット構成の作成も顧客ルールを元に自動的に表示し入力ミスを大幅に削減できます。
必要ロゴの追加が可能
GHSラベルに「合格品」を証明するロゴや「RoHS」証明のロゴ、容器を上向きに指示する「矢印」ロゴの表示など、導入企業のご要望に合わせたロゴ追加、製品別に異なる特殊ロゴの追加も可能です。
必要項目を保存するQRコード
製品コード・製品ロット・製造日付や消費期限日などのラベル印字項目は、QRコード内に保存し製品入出庫でのスキャン運用に利用ができます。
製造委託や販売元の情報は紐付け管理
弊社のお客様は製造委託先と販売元が複数あり、間違った組み合わせ印刷は問題となるため、それぞれの組み合わせ情報を管理。
販売元を選択すると製造委託先が自動的に表示される仕組みを採用しています。
中国導入で知っておきたいGHSプリンター選びのメリット&デメリット
GHSラベルを印刷する代表的なプリンターは、リボン使用の「ラベルプリンター」と「インクジェットプリンター」の2種類です。
事前印刷したGHSラベル運用は「生産日」や「消費期限」、「ロット」をQRコードへの追加が難しく、プリンターで発行し生産稼働時に工場内でラベル印字が必要となります。
GHSラベルプリンター運用の特徴

利用用途で選びたいGHSラベルプリンター
プリンターは印字幅が広い機種(160mm~200mm)と印字幅が普通(105mm幅)の2種類から選択となります。
ドラム缶など貼り付け面積が広く印字エリア確保が必要な場合は、幅広タイプのラベルプリンターで印字。
容器が小さい製品は105mm幅のラベルプリンターで印字運用する場合が多いです。
いずれのラベルプリンターでも注意する点は「赤枠印刷」の有無についてです。
一般的なラベルプリンターは一色刷り(基本は黒色リボン使用)のため、黒と赤の二色刷りが可能なラベルプリンターは対応機種が限られます。
一色刷りラベルプリンターで運用を検討する場合は、事前に赤枠印刷したラベルを準備。ただし製品別に「絵表示(シンボル)」数が異なるため、赤枠数の異なるラベルを在庫準備し製品別にセットして印字します。
二色刷りプリンター運用は赤枠印刷が可能なため、共有利用のラベルのみでOK。少量の在庫数で管理が可能です。
一色刷り運用は異なる赤枠ラベル印刷が必要なため在庫量が多くなり、ランニングコストが増える恐れがあります。
インクジェットプリンター運用のGHSラベル発行
インクジェットプリンター運用のメリットはフルカラー印字による見栄えの良さと、カラー印字となる赤枠やロゴの事前印刷の準備が不要な点です。
また白地ラベルに直接印字となり、ラベル在庫も少量で済みます。
ただしラベルプリンターと比較すると印字速度が多少遅く、フルカラーのためランニングコストが高め。
製品の液漏れが生じた場合にじみなど耐性が弱い部分があります。
ラベルプリンター運用は耐性に強い「レジン系リボン」や「合成紙ラベル」等の選択肢の幅があり、インクジェットはラベルに保護用ラミネートシートを貼り付け、耐性をカバーするなど運用時に工夫が必要です。
※耐性のあるリボン印字でもラミネートシートを採用する場合もあります。
GHSラベル運用のまとめ
いかがでしたか?
GHSラベル発行運用は現場スタッフが間違えない管理体制をシステム導入で構築し、赤枠印刷やラベルサイズの面から導入するプリンターを検討する必要があります。
弊社はお客様にあったシステム提案をご提供いたします。まずは一度ご連絡ください。
その他弊社のラベルプリンターに関する開発導入事例は「コチラをクリックして」ご覧ください。ラベルを利用したソリューションをご紹介しています。